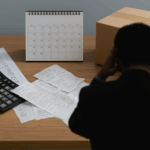税務調査とは?仕組みと流れ、正しく向き合うためのポイント

法人税や所得税など、私たちが納める税金は「自主申告・自主納税」が原則です。つまり、自ら税額を計算し、正しく申告・納付することが求められています。
しかし現実には、計算ミスや記載漏れがあったり、時には意図的に税額を少なく申告しようとするケースもあります。そうした事態を防ぎ、すべての人が公平に税金を負担できるようにするために、税務調査という仕組みが存在します。
この記事では、税務調査の種類や流れ、そして上手に向き合うための心構えについて解説します。
税務調査とは?その目的
税務調査の目的は、提出された申告書が適正に作成されているかを確認することです。言い換えれば、「税務署による確定申告書の採点」とも表現できるでしょう。
確定申告書を提出してホッとする方も多いかもしれませんが、学校のテストが答案提出だけで終わらないように、税務申告も「提出後の確認」が残されています。
税務調査の種類は2つ
税務調査には大きく分けて以下の2種類があります。
1. 任意調査(通常の税務調査)
通常、税務調査といえばこの任意調査を指します。税務署の調査官が申告内容の確認のために行うもので、原則として事前通知があり、納税者の協力のもとで実施されます。
「任意」とは言っても、正当な理由がない限り拒否は難しいのが実情です。
2. 強制調査(査察調査/マルサ)
悪質な脱税などが疑われる場合に、国税局の査察部門(いわゆる“マルサ”)が行うのが強制調査です。これは裁判所の令状に基づき、納税者の同意なしに捜索や差押えが行われるケースもあります。
税務調査の流れ
税務調査は、いきなり事務所に来て始まるわけではありません。一般的な流れは以下の通りです。
1. 事前通知
通常は、税務署から税理士を通じて調査日程や調査対象期間について事前に連絡があります(任意調査の場合)。
2. 調査当日:調査官の訪問とヒアリング
当日は、調査官が身分証明書を提示してから調査がスタートします。まずは事業主へのヒアリングとして、以下のような内容が確認されます。
- 開業までの経歴
- 現在の事業概要
- 業種の特徴や最近の業績状況
- 帳簿の作成・保管状況、現金や預金の管理方法 など
このやり取りを通じて、調査官は調査すべき重点項目を絞り込んでいきます。
3. 帳簿・書類の確認
ヒアリングの後は、帳簿・領収書・契約書などの資料と申告書の内容を突き合わせてチェックが行われます。
4. 調査後の対応
申告内容に問題がなければそのまま調査終了です。誤りや修正すべき点が見つかった場合は、後日顧問税理士へ連絡があり、必要に応じて修正申告や追徴税額の納付を行います。
税務調査は“経営改善”のチャンスでもある
税務調査が入ると聞くと、どうしても「怖い」「面倒」とネガティブに捉えがちですが、見方を変えれば、自社の経理や管理体制を見直す絶好の機会とも言えます。
例えば――
- 経理の弱点や見落としが明らかになる
- 従業員の不正が発覚する場合もある
- 他社事例や改善点を税務職員から教えてもらえることもある
つまり、調査を通じて、自社の経営をより強く、安定的にするヒントを得られる可能性があるのです。
まとめ
税務調査は、全納税者が公平に税負担を果たすための重要な仕組みです。確かに緊張する場面もありますが、正しく対応すれば何も恐れる必要はありません。
税務調査を「経営を見直すチャンス」と前向きにとらえて、自社の体制強化に活かしていきましょう。